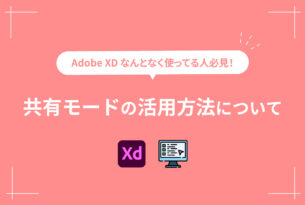#Webデザイン
デザイナーなら知っておきたい色の知識【環境・文化で変化する見え方・感じ方編】


…ぁ、っという間に2019年の半分が終わりました。オリンピックのチケット、皆さん取れましたでしょうか…。
どうも、SPCデザイナーAです。
前回に続き、デザイナーなら知っておきたい色の知識、今回は環境や文化によって変化する見え方や感じ方の違いについて認めていきます。
どうも、SPCデザイナーAです。
前回に続き、デザイナーなら知っておきたい色の知識、今回は環境や文化によって変化する見え方や感じ方の違いについて認めていきます。
前回記事はこちら→デザイナーなら知っておきたい色の知識【色彩心理学編】
地域によって色の見え方が違う

まず、色の見え方は光の波長によって変化します。
よって太陽光が丸い地球に当たった場合、太陽との距離が遠い北極点・南極点と、距離が近い赤道とでは異なります。
赤道付近の明るさと比べると北ヨーロッパ地域の明るさは約1/4位になるとされます。明るい太陽光の下では、明るく鮮やかな色に対する反応が敏感になるのに対し、 太陽光に恵まれない北ヨーロッパのような地域では、鮮やかさを抑えたニュアンスのある色に対する美的感度が高まるようです。
そして、赤道に近づくほど赤みが強調され、赤道から離れるほど青みが強調されるという特性があります。よって、国により自然界の色みが変わってしまう事があります。
よって太陽光が丸い地球に当たった場合、太陽との距離が遠い北極点・南極点と、距離が近い赤道とでは異なります。
赤道付近の明るさと比べると北ヨーロッパ地域の明るさは約1/4位になるとされます。明るい太陽光の下では、明るく鮮やかな色に対する反応が敏感になるのに対し、 太陽光に恵まれない北ヨーロッパのような地域では、鮮やかさを抑えたニュアンスのある色に対する美的感度が高まるようです。
そして、赤道に近づくほど赤みが強調され、赤道から離れるほど青みが強調されるという特性があります。よって、国により自然界の色みが変わってしまう事があります。
地域特性と風土の関連性

その土地によって色の見え方が違う事に加え、季節や景色・景観によっても色の印象は大きく関係します。
季節による気象状況によって実った植物、その土地のもので作られた景観、それらの状況下で培われた配色感があります。海外に行った時に、日本にはない珍しい色使いの洋服や装飾品を見つけ、気に入って購入したは良いものの、旅行先では素敵に見えたものが、日本で身につけてみると派手過ぎたり、違和感を感じた経験はありませんでしょうか。
このようなケースは、地域の気候や風土に色が大きく関係している事で起こります。色は、太陽の光や空気の透明度、環境の色との対比によって、見え方が大きく異なります。つまり、美しく見える色はその地域によって異なります。日照率の強い太陽光のハワイやグアムなどで買った水着が、日本でも同じように美しく見えるとは限りません。赤やゴールドの鮮やかな色で彩られたタイの寺院などの下では、多色配色の鮮やかな服装でも違和感を感じませんが、閑静な住宅街では違和感を感じてしまうでしょう。
環境に培われた感覚により、南国の地域では鮮やかな暖色系の色が好まれ、日照率が低い北ヨーロッパのような地域では、色みを抑えた寒系の色が一般的に好まれるようです。
認識や感覚の仕方の違い

色彩感覚の違い
日本人の中では常識的な色であっても、海外ではまた違った色彩感覚で捉えられ、ズレが生じるケースがあります。
例えば日本で虹の色といえば、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の7色ですが、イギリスやアメリカでは赤・橙・黄・緑・青・紫の6色で認知されており、アフリカのバサ語族は赤・黒の2色で認知されているそうです。
例えば日本で虹の色といえば、赤・橙・黄・緑・青・藍・紫の7色ですが、イギリスやアメリカでは赤・橙・黄・緑・青・紫の6色で認知されており、アフリカのバサ語族は赤・黒の2色で認知されているそうです。
目の色によって見え方が変わる
人間は人種によって目の色が違い、それにより光の感じ方や色彩感覚が影響を受ける場合があります。光の感じ方はメラニン色素の数によって変わります。メラニン色素は黒茶色をしており、太陽光に含まれる有害な紫外線から肌や目を守る役割があります。メラニンが多く含まれる、目の色が黒いアジア人より、目の色が青い白人は2倍眩しく感じるそうです。そのため、国によって電気の明るさが異なったり、白人の多くの人がサングラスをしていたりします。このような眩しさの違いにより、色彩の好みが変わる事があります。
文化で培われた色への認識で差が生まれるケース
前回の色彩心理学話にも紐づく話ですが、歴史や文化によっても色にイメージがつく事があります。
例えば日本では、西暦603年に聖徳太子が作った官位制度「冠位十二階」と呼ばれる人の貴賤を表す序列がありました。この冠位十二階は「徳・仁・礼・信・義・智」の儒教の徳目で分けられ、それぞれ冠の色を「徳=紫・仁=青・礼=赤・信=黄・義=白・智=黒」の色分けと大・小をつけて区別したそうです。ここで一番上の官位で尊いとされている色が「紫」であったため、今でも日本人の中で優雅な色というイメージが強いという説があるそうです。このように、歴史的背景から色へのイメージがつく事があります。
例えば日本では、西暦603年に聖徳太子が作った官位制度「冠位十二階」と呼ばれる人の貴賤を表す序列がありました。この冠位十二階は「徳・仁・礼・信・義・智」の儒教の徳目で分けられ、それぞれ冠の色を「徳=紫・仁=青・礼=赤・信=黄・義=白・智=黒」の色分けと大・小をつけて区別したそうです。ここで一番上の官位で尊いとされている色が「紫」であったため、今でも日本人の中で優雅な色というイメージが強いという説があるそうです。このように、歴史的背景から色へのイメージがつく事があります。
歴史的背景から色の思想を読み取る上で、最も参考になるポピュラーなものに国旗が挙げられると思います。国の象徴とされるものにどのような思想や意味が込められて配色がなされているかを知ると、その国の歴史的背景や思想が読み取れるかもしれません。そして、調べてみると中国の主要Webサイトは赤が多用され、フィンランド等の北欧の主要なWebサイトはオーガニック色が多用されている傾向が分かります。培われたその配色感がその国々のWebサイトにおいても現れている事が伺えます。
【中国サイト参照】
鱼摆摆网:https://www.yubaibai.com.cn/
ZCOOL站酷:http://www.zcool.com.cn/event/xadongman2013/
凤凰网:http://www.ifeng.com/
鱼摆摆网:https://www.yubaibai.com.cn/
ZCOOL站酷:http://www.zcool.com.cn/event/xadongman2013/
凤凰网:http://www.ifeng.com/
【北欧サイト参照】
フィンランド政府観光局:https://www.visitfinland.com/fi_FI/web/guest/finland-guide/home/
アラビア(テーブルウェア):http://www.arabia.fi/
ヘルシンキ・ヴァンター空港:https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa
フィンランド政府観光局:https://www.visitfinland.com/fi_FI/web/guest/finland-guide/home/
アラビア(テーブルウェア):http://www.arabia.fi/
ヘルシンキ・ヴァンター空港:https://www.finavia.fi/fi/lentoasemat/helsinki-vantaa
いかがだったでしょうか、知れば知るほど奥が深い色の知識。
ものづくりの担い手としてはこういった事柄を抑えて制作が出来る事で、よりハイクオリティなものが生み出せるのではないでしょうか。
ものづくりの担い手としてはこういった事柄を抑えて制作が出来る事で、よりハイクオリティなものが生み出せるのではないでしょうか。
CATEGORY
TAG
htaccess
補助金
助成金
Webブラウザ
キックオフミーティング
サブディレクトリ
サブドメイン
SSL化
広告審査
TikTok広告
審査落ち
広告ポリシー
CMS
Webサイト制作
プラグイン
ECサイト制作
採用活動
ツール
Google広告
SNS広告
Web広告
セキュリティ
XD
SNS運用
アニメーション
採用サイト
Webデザイナー
Webディレクター
SEO対策
ドメイン
Instagram
YouTube
ECサイト
Wordpress
Webディレクション
Googleアナリティクス
EFO
Illustrator
LPO
Facebook
リスティング広告
コンテンツSEO
Webマーケティング
ライティング
Webデザイン
Photoshop
GoogleAnalytics
アクセス解析